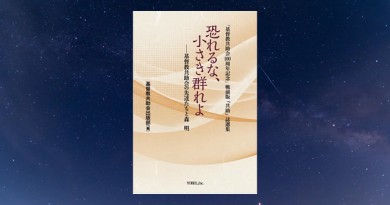四 アジアへの視点―和解を生きる―1965 年~1989 年— 山本精一著 『 90 年史』P155
『基督教共助会九十年―その歩みの想う―』(2012 年 基督教共助会)より
一九六六年四月から五月にかけて、和田正と澤正彦は、戦後初めて共助会からの使者として、それぞれにとっても初めての韓国訪問を行った。それは、韓国にいる四人の共助会員を問安するためであった。この安の機縁となったのは、 その三年前に韓国を訪れていた李仁夏が、敬愛する先輩李英環、洪彰義との再会を果たした際に、李 英環が李仁夏に向けて語った言葉であった。それは、「あの方たち(奥田成孝や和田正のこと)には地上ではもう会 えないかも知れませんね。両国の関係がこの調子ではね・・・・・・」「でも会いたいな! 再び会えたら、涙ぐむでしょうね」というものであった。
李仁夏がこの二人と初めて出会ったのは、戦時下、京都の和田正の自宅で行われていた聖書研究会においてであっ た。李仁夏は、一九四一年、当時韓国で通っていた中学校が植民地支配下の弾圧により閉鎖されたことによって、 多くの葛藤を抱きながら勉学の機会を求めて日本に渡り、京都の東寺中学に「岩城正男」という名前で第二学年編 入をしていた。編入した李がまず経験したのは、同級生や一部教師たちによる植民地出身者に対するいじめや罵倒、 特高刑事による恫喝的捜査であった。和田が、東寺中学に英語と数学の教師として赴任してきたのは、ちょうどその年の秋のことであった。その後、下校時の市電の中での遭遇、李の下宿と和田の自宅との近接といった、数々の 摂理的な偶然が重なって、和田による李の下宿への訪問、和田自身の申し出による英語のプライヴェイト・レッス ンが和田の自宅で始まる。この交わりの中で、和田はやがて自らのキリスト教信仰を明らかにし、マタイによる福音書の英訳テクストを用いたレッスンは、ごく自然な形で聖書研究会へと発展する。そこには朝鮮半島出身の中学生たちが集まってきた。聖書の研究を終えると、これら若者たちは和田に祖国で起きている日本総督府による弾圧統治につき、やり場のない思いを吐露し、和田もまたそれに真摯に耳を傾け続けていた。こうして李は、和田との交わりを通して十字架と復活のイエスへと眼を開かれていくという経験をしていた。
一方、李英環は一九四○年、洪彰義はその一年後に、植民地下の朝鮮から、それぞれ留学生として日本の山口高等学校に入学していた。祖国朝鮮における彼らのもっとも多感な少年時代もまた、日本の強圧的な植民地支配による民族迫害の経験の中に投げ込まれていた。それぞれの複雑な背景を背負いながら、この二人は、山口高等学校において初めて出会う。そこには共助会員であった堀信一が英語の教授として勤務していた。彼らは、さらに、郭商洙、李台現といった同高校に在学していた朝鮮半島出身の友人たちと共に、堀の自宅で毎週土曜日行われていた聖書研究会に出席し、霊的な交わりを経験する。やがて李英環は一九四二年に、洪彰義はその翌年の四三年にそれぞれ京都帝大の医学部に進学する。その際、彼らは堀から北白川教会を紹介され、そこに出席するようになり、奥田、和田をはじめとして、北白川教会の交わりのうちで信仰生活を続けていた。郭商洙と李台現とはそれぞれ東京帝大に進んだが、そのとき同じく堀の紹介により、共助会員本間誠の牧会する目白町教会に出席した。さらに彼らは、先述した和田の自宅で行われていた聖書研究会にも出席するようになる。中学生であった李仁夏と初めて出会ったのは、この場においてであった。後年李は、この時の二人の先輩たちのことを「高い山のような存在で、兄のように慕ったが、理科系の学生がディヴォーショナルな姿勢で聖書と取り組む姿勢に深く打たれていた」と感謝に満ちて述懐している。
一九四五年、和田が祈りのうちに示されて、中国奥地伝道を志し「自分は何もできない。・・・・・ほんとうに何もで きないが、中国へ行って、ただ一人の中国人にだけでも仕えて死んでいきたい」と中国へと旅立とうとしたとき、李英環、洪彰義は出航地の大阪港まで見送りに同行した。その際彼らが和田に語った別れの言葉は、次のようなものであった。「先生は日本から見れば遠く離れた満州へ行かれるわけですけれども、私たちの国から見ればもっと近いところにいらっしゃるのですから、本当にうれしいです」。主にある交わりを結んだ和田の戦時下におけるこの出処進退は、被植民地出身の二人の留学生たちにとって、生涯忘れることのできない喜びの出来事となった。この「近さ」とは、単なる距離や位置関係のことではない。常識的見地から見れば無謀ともいえる和田の信仰的決断は、彼らにとっては、徹底的に奪われ見下されてきた自分たちの祖国朝鮮の孤立と屈辱の中に、和田があたかもその責めを負うかのようにして全身全霊で近づいてくる出来事として受けとめられていたことが、この別れの言葉から伝わってくる。この後まもなく、二人はそれぞれ朝鮮に戻り、京城帝大医学部生として日本の植民地支配からの解放の時を迎える。しかしそれも束の間、その後ただちに南北分断、南北動乱(朝鮮戦争)、家族離散、軍事独裁政権という言語を絶する苛烈な民族的苦難の中に投げ込まれる。本節冒頭に紹介した李英環の言葉は、以上のような歴史的背景の中から発せられた言葉であった。しかしこの言葉は、現在とは比較にならない困難な状況のなか韓国を訪ねた李仁夏によってしかと聴きとめられ、日本にいる共助会の祈りの友垣に届けられた。この言葉のうちに息づく深い霊的な渇きに促されて、和田と澤が共助会を代表して旅立ったのは、その三年後六六年のことであった。それは また、
本章一―(四)で触れた日韓基本条約締結一年後のことであった。その条約が締結された六五年に、東京神学大学の学生であった澤正彦は、李仁夏が母校である東神大で行った講演「民族間の和解を目指して」を聞きながら、心を震わされる経験をしていた。それは、澤にとって「雷の中から轟くように聞こえる天啓の言葉」、このような経験によって、澤もこの韓国訪問の旅へと押し出されていた。出発に先立っては、東京周辺の共助会員 たちが中心となって、中渋谷教会において二人の訪韓を覚え祈る集いがもたれた。
韓国訪問への準備として、和田は、朝日新聞韓国特派員(西村敏雄)の書いた書物(『私は見た・韓国の内幕』) を読み、朝鮮総督府による弾圧統治の実態の一断面を書物を通して初めて具体的に知り、大きな衝撃を受ける。
韓国在住の共助会員たちから手厚く迎えられた二人であったが、ソウルの延世大学の連合神学大学院でもたれた集会の雰囲気はまったく異なっていた。しかも和田が後に述懐するように、その場の雰囲気の厳しさは、和田自身が当初その場で感じていた厳しさよりも実際にはさらに厳しいものであった。そこに集まってきた二、三〇人の韓国人の院生や学生たちは、みな日本統治時代の苦難の経験の生き証人たちであった。 さらに前年には、すでに触れたように、日本の戦争責任を空洞化する「日韓基本条約」が、市民・学生の激しい反対にもかかわらず、両国政府間において締結されたばかりであった。したがって参加者の中には、和田と澤を、日本政府から派遣されてきた者と疑い、 「今晩の話もきっと口頭で謝るだけであろう。しかし半世紀の民族の歴史を奪って行った彼らの安っぽい口先だけの謝りを受け入れることができるというのか」と怒りを込めて語る者もいた。このことは、欧米キリスト教国がラテンアメリカ、アフリカ、アジアで植民地侵略を行ったとき、キリスト教宣教師たちの多くが、本国政府と一体化して侵略に加担してきた罪責の膨大な史実に照らすならば、さらにはまた植民地朝鮮で日本の教団統理であった富田 満が朝鮮のキリスト者たちに神社参拝を説得した直近の史実に照らすならば、歴史的に深い背景を持った当然の反応であった。その意味において、和田と澤は、この時、延世大学の集会において、植民地支配による深い傷を負った若いキリスト信徒たちの厳しい応対を通して、何にもまして彼我の間に横たわる癒しがたい断裂の深さに直面していた。
この話と座談を終え、厳しい応対に内心打ちひしがれていた和田のところに、初対面の参加者の中から一人の大学院生、尹鍾倬が歩み寄ってきた。彼もまた、幼時より植民地支配の苛烈な弾圧と忘れることのできない屈辱を、学校・教会・家庭といった生活現場において、自分自身や父の経験を通して怒りとともに胸底深くに刻み込んでいた。ところが、尹は、十字架の下での赦しをひたすらに請いねがう和田と澤の話の内容と姿勢、すなわち存在のありように触れ、日本と日本人に対する消し去りがたい敵愾心を抱き続けている自己自身の最も深い問題を、そのとき自ら呻きつつ十字架の下に差し出したのであった。そして底深い憎悪心と敵対感をみずから告白し、あろうことか今度は和田に主の十字架の下での赦しを求めたのであった。赦しを受けることなど望むべくもない民が、赦しを受けることを請い続けねばならぬ民の一人から、逆に赦しを請われるという出来事が、一九六六年四月ソウルの大学の片隅で生起したのであった。和田、澤と尹にとって、この出来事は贖罪的和解の決定的な経験となった。これは、単なる情動的一致でも美談でもない。十字架の和解の福音に生かされた者はその和解の福音を新たに生きる。この 厳しくも豊かな恩寵を身をもって経験した和田と澤は、この出来事以降新たに、それぞれに固有の仕方で、日韓の 間の深い溝に身を投じ続ける。
それは、見方を変えれば、その会場に集った尹以外の青年たちに代表される人々との間にいまだ和解が実現していないことを、告知し続けるものである。そのために捧げられねばならない祈りと業に、 彼らは押し出されていった。この事は、共助会に、さらには日本のキリスト者に、ひいては日本社会に、「安っぽい 口先だけの謝り」とは異なった道を、静かにしかし厳然と指し示している。