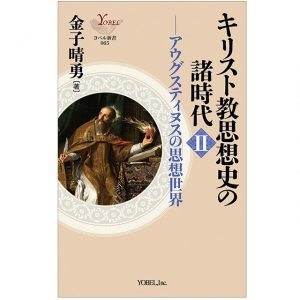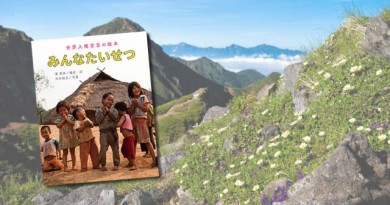「不安な心」から身体 ― 精神 ―霊の「霊性の人間学」へ評者: 出村 和彦
金子晴勇『キリスト教思想史の諸時代Ⅱ― アウグスティヌスの思想世界』
本書は、『キリスト教思想史の諸時代』シリーズ第二巻で、古代末期、キリスト教と人文学を架橋したアウグスティヌスの探求者としての生涯の思想を「人間学」の観点から総合的に提示するものである。著者の長年の研究を透徹した形で表現する新書であり、バランスよくアウグスティヌス思想にわたしたちを導いてくれる。
かつて若き著者は、『告白録』における「不安な心」に焦点を当て、神の前に立つ人間の心の動態を、前置詞ad te(神への対向性)、abs te(神からの転落性)、 in te(神のうちに、神にしたがって)の三方向によって抉り出した実存論的解釈(第三章)を鮮烈に提示し、学界に大きな影響をもたらした。今や本書では、「不安の心の哲学」から「霊性の人間学」へアウグスティヌスの精神的発展をより掘り下げて考察するに至っている(第四章)。本書のアウグスティヌスの「心の哲学」は、単に個人的な「不安な心」に定位するのではなく、神に開かれた霊性の観点から考察される。この霊性は人間に共通の身体―魂―霊の作用の中心である「心」の探求である。
第六章「心の機能として霊性」で著者は、「神の知恵が最高の至福を伴ってその源から汲まれるとき……その身体は如何程にすぐれているのであろうか。それは肉の実態を持ちながらも肉的な壊廃はまったくなく、魂的ではなくて霊的になるであろう」という『神の国 第二二巻』を引用し、「これがアウグスティヌスの霊性の理解であって彼は最晩年のペラギウス論争の諸著作でもペラギウスの人間の本性の立脚した自然主義的な道徳哲学と対決」していることを明らかにし、「神秘主義が説く観照との合一についてはいつも終末論的留保がなされ、希望の下に置かれた」(141頁)と指摘している。
ちなみに古代の「哲学(原義は知恵を愛すること)」というと、専ら懐疑派等のヘレニズム・ローマ哲学やプラトン主義を指すものとされがちであるが、著者は、理性と信仰の連関についてのアウグスティヌスの独特な思想を説明し(第五章)、「愛によって働く信仰」において「最高の知恵は神であり、神の礼拝が人間の知恵である」とし、「人間であるイエスを通して神なるキリストへとわたしたちは導かれる」という思想を強調して、そのような神への愛こそ、神から与えられたものであり、その神の愛が注がれるのは「わたしたちの心」であって、アウグスティヌスは「このような心は聖霊の働きと一緒に「霊」となって起こっていると考える。ここにはカリタス(聖なる愛)の論理が明瞭に認められる」(163頁)とする。
さらに本書は、アウグスティヌスの後期思想を理解するのに格好の手がかりを与えてくれる。第七章「ペラギウス批判と霊性の復権」は、アウグスティヌスとペラギウスの恩恵論の特徴と相違について実によく整理して記述されており、これに続く第八章「原罪と予定の問題」は、アウグスティヌス自身の「情欲」への取り組み等、彼の思考の本質を提示する周到な説明がなされていて必読である。
「予定」に関しても、カルヴァンの「予定説」との相違について有益な指摘(206頁)がある。
本書は、アウグスティヌス原典翻訳に長く尽力された著者の成果であり、まさに「青年時代に求めたものは、老年において豊かに与えられる」(ゲーテ)喜びそのものである。(岡山大学大学院ヘルスシステム統合科学研究科教授)