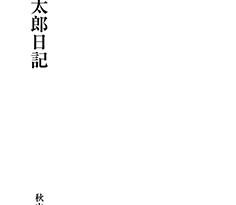下村喜八著『苦悩への畏敬 — ラインホルト・シュナイダーと共に』山本精一
ナチス支配下のドイツにあって不屈の抵抗者であった詩人ラインホルト・シュナイダー。その作品に、著者は、留学先のドイツで初めて出会う。1989年の事である。その言葉に「身震いするような感動をおぼえた」著者は、以後、留学当初の研究計画を擲なげうって、シュナイダーの作品に心魂を注いでいかれた。それは、著者の人生に「転換点」(3頁)をもたらす出来事となった。そのような並々ならぬ出来事を著者に惹き起こしたシュナイダーとは、いったい何者なのか。
シュナイダーは、腸閉塞と深刻な自殺願望という身心の苛酷な病を終生抱えていた。しかしその身心の病は、シュナイダーにとって、キリストの十字架の苦難そして恵みが到来する「通り道」(92頁)となった。彼はその病を負いつつ、全体主義国家ドイツの内に踏みとどまり、その悪魔的な体制に明確な否を表明しながら、すんでのところで生還し得た稀有な人であった。彼は、病に苦しみながら、その魂は時代のなかで苦しむ人々へと一貫して向けられていた。彼のその共苦と抵抗の文学活動に、ヒトラー独裁下で絶望していた多くの一般市民が、どれほどの励ましと慰めを与えられていたのか。その事をもまた本書は教えている。そのようなシュナイダーの生き方の根底には、キリストの十字架の苦しみを、今このとき自らの置かれた歴史的状況のなかで絶えず新たに想起し、畏れと感謝をもって受けとる信仰があった。シュナイダーは、そのようにして、キリストの苦難と隣人の苦難に集中する生を暗い時代の中で生きた人であった。その生は、何よりも日々の祈りと密接不可分のものであった。著者は彼を「祈りの人」(4章)と呼ぶ。
その祈りの人シュナイダーは、「キリストに出会い、その愛に生かされて苦悩を共苦と思いやりに変えた」(4頁)人であった。しかしそれにもかかわらず彼は、著者留学時には、ドイツ国内においてさえあまり読まれなくなっていたという。しかし著者は、そのシュナイダーの作品にこそかの地で出会い、身震いするほどの大きな衝撃を受けて、彼の作品に鋭意専心していかれた。以後著者は、シュナイダーの言葉と向き合いつつ、問い問われる道をひたすらに歩んでこられた。それは著者に「シュナイダーと共に」(本書副題)との祈りをもたらすものとなった。本書はかくして、時と所とを超えて生じた、ラインホルト・シュナイダーと著者との比類なき出会いの軌跡を伝えるドキュメントとなっている。
本書は十二章から成る。紙数制限上、その内容について区々立ち入ることはできない。ただそれらはすべて、本誌に発表されたもの、あるいは京阪神共助会の修養会、日本基督教団北白川教会で語られてきたものを母体としている。それゆえ本書は、著者の霊的母体をなす交わりと礼拝の場で、著者が生ける神の前に立って語ってこられた告白証言の集成である。
その全体を貫く根本テーマが、「苦悩への畏敬」(本書タイトル)である。それを章題とする第3章が、本書の核心をなす。その第3章を読む上で、第1章もまた重要である。
本書の1章(2001年)、11章(1997年)以外は、すべて2018年から2021年というここ数年内に語り記されたものである。著者は何故シュナイダーについて語り記すのか。そこには著者の三つの熱い祈りがある。一、「時代の中にある自分の生きかたを検証しなおしたい」。二、「彼の言葉と生きざまを通して、彼の内に働かれたキリストを仰ぎたい」。三、「時代と闘う勇気を得たい」。この根底にある祈りのうちで、著者は、「核によるホロコースト」の狂気に事実直面している21世紀前半の今、「この困難な時代の中で苦悩しておられる人たちと共にいかに生きるべきかを考え、共に祈り、一人では担いきれない重荷を担いあうことによって、時代に対する私たちの責任を果たしてゆきたい」(8頁)と告白される。
著者は、本書において、「キリストとの共苦」「苦しむ隣人との共苦」のうちにこそ望みを賭けたシュナイダーを繰り返し心に刻んでいる。それは、単なるシュナイダー礼賛といったものではない。何よりも、シュナイダーが、絶望するしかない時代のなかで、イエスの苦しみに連なる人間の生を深く感謝して生きた事、苦しむイエスの十字架を日々新たにわが内に受け容れていったという事、その一切の根底に、キリストはこの地上でわれわれのために、この時代のために、神を見失う苦しみのうちにあったという事。それらの事をこそ、著者は本書で繰り返し心に刻みつけている。
著者は、この時代のただなかで、キリストと共に歩んだ「シュナイダーと共に、彼に倣って生きたい」(6頁)と告白されている。しかしその告白は根本的には、著者からわれわれに向かって、さらには「この困難な時代の中で苦悩しておられる人たち」に向かって発せられている呼びかけである。その呼びかけを聞くわれわれは、自己自身の罪の、この時代の罪の深淵のうちにある。しかしそれと同時に、その中にこそ来たりたもうた救い主キリストの「裸の十字架」が、聖書テクスト(エレミヤ書、福音書、パウロ書簡)を通して、またルターやシュナイダーを通して、ひたすらにさし示されている。
同時に著者は、本書において、ご自身のこれまでの歩みについて立ち入って語っておられる。そこには、著者ご自身の誕生・幼少期から学生時代、さらには大学教員となってから現在に至る、折々の濃密で重要な記憶が、かつまた師友先達から受け取ってこられた生涯の宝とされる言葉と出来事が、さらには古今の神学者・思想家・政治家の言葉が、シュナイダーの共苦の信と織り合わされて、考察されている。それらは、本書にさらに一層の奥行きと広がりを与えるものとなっている。著者の祈りにアーメンと唱えつつ本書を読み終えた事だった。 (日本基督教団 北白川教会員)