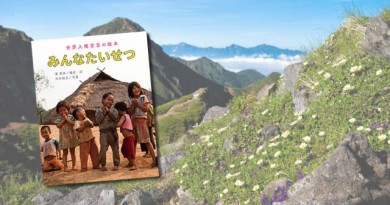東西霊性の在所を照らす 片柳榮一
【書評再録 「本のひろば」2022年1月号】
金子晴勇著『東西の霊性思想 ― キリスト教と日本仏教との対話』
人間学的視点という明確な方法論をもってキリスト教思想史研究の分野でいつも新鮮な刺激を与え続けてきた著者は近年、その方法をさらに霊性思想において深め、旺盛な著作活動を展開している。そしてその探求の一つの到達点が本書『東西の霊性思想』と言えよう。単に東西の思想を比較しているのでなく、著者が長年その研究に打ち込んできたキリスト教思想と、私たちがそこに生きている日本の文化・思想、殊に仏教を、豊富な文献を用いて精査し、自らのうちに見つめ直しているのである。
「霊性」というそれ自体概念化しにくい事柄に、著者はその機能面より接近し、そこに三つの基本的な働きを見ている。一つは感得作用であり、「外的な感覚ではなく、心の奥深く感じ取ること」( 25頁)であるという。このことを明瞭に表明しているのはパスカルであり、「神を直観するのは心であって理性ではない。信仰とはそういうものなのだ。心に感じられる神」(パンセL. 424)であるという。第二は自己を越えて神に向かう超越作用である。これはアウグスティヌスの次の言葉に最も明らかに示されている。「外に出て行こうとするな。汝自身に帰れ。内的人間の内に真理は宿っている。そしてもし汝の本性が可変的であるのを見出すなら、汝自身を超越せよ」(『真の宗教』XXXIX, 72)。
そして第三の機能は、心身を統合するものとしての霊の作用であるという。そして著者は現代、ことに日本の大きな危機の根源を、こうした霊性が無視されてきていることに見ている。「これまで日本では明治以来、ヨーロッパ文化は近代化や合理化の典型として賛美され、模倣されてきた。それゆえヨーロッパを学ぶことは。ルネサンス以降の近代化と合理化を学ぶことであった。……ところが日本におけるこれまでのヨーロッパ思想の受容は生命の根源である霊性を除いた、亡霊となった屍を有り難く採り入れたにすぎなかった。したがってヨーロッパ思想の生命源である霊性を学び直すことは今日きわめて重要である」(16頁)。
この書の導きの糸になっているのは、西田幾多郎の次の言葉であろう。「われわれの自己の根底には、どこまでも意識的自己を越えたものがあるのである。これは我々の自己の自覚的事実である。自己自身の自覚の事実について、深く反省する人は、何人もここに気附かなければならない。鈴木大拙はこれを霊性といふ」( 19 頁)。著者はこのような問題意識をもって、旧新約聖書、キリスト教教父、神秘主義者、ルターを始めとする宗教改革者などのキリスト教の霊性思想と、万葉集以来の日本文学や、また鎌倉仏教において類まれな形で現れた日本的霊性の特徴、更には白隠、明治のキリスト者、植村正久、内村鑑三、又あまり知られていなかった新井奥邃や綱島梁川の神秘主義的体験にもみられる霊性思想を丹念に掘り起こしている。法然や親鸞の凄絶なまでの「如来の本願に対する絶対信仰」(124頁)をあらためて丹念に教え示され、著者の共感の深さにも感銘を覚える。
今日本に生きる私たちは、霊性という点においては、果てしない荒れ野の中に打ち棄てられている。まさしく生ける命の源を断たれているかの如くである。そのような中で本書は、命の水の在り処をはっきり示している。
(聖学院大学客員教授)(四六判上製・二八〇頁・定価一九八〇円・ヨベル)